第28章 新技術への対応 |
||
| アシロマ会議は興奮させられると同時に混乱に満ちた事件であった。興奮させられたと述べたのは、(組み替えDNA技術が可能とする)科学的冒険のスケールの大きさ、研究の拡がり、それに加え、誰も科学者の力と責任に無関心で居られないと云うこと、の為である。混乱に満ちたと述べたのは、基本的な問題が非常に混乱した状況で取り上げられたか、或いは、全く議論されなかったからである。未知との境界にあって、利益と危険性の解析は、「何も分からない」を真ん中に置き、議論は膠着してしまった。実験もせず、最小限のリスクすら取らず、どうやって現実に決定を下せただろうか? (Philippe Kourilsky; Les Artisans de l’heredite (Paris, Editions Odile Jacobe) この引用は、D. Fredrickson, The Recombinant DNA controversy A Memoir Science, Politics, and the Public Interest 1974-1981, ASM Press, 2001の序文に引用されている。社会的に影響があり、且つ未知の領域を前にした問題につき、科学者が判断を迫られる状況をうまく要約している。 前にも述べたように、組み替えDNA技術は、DNAを特定の場所で正確に切断出来る制限酵素を発見した事により可能となった。多くの制限酵素は、2本鎖DNAを段違いに切断(staggered
cut)する。すると、同じ酵素で別のDNAを切って混ぜれば切断点の飛び出た同士が水素結合により繋がる事となる。2つのDNAは更にDNA修復酵素で完全に一つになる。 |
||
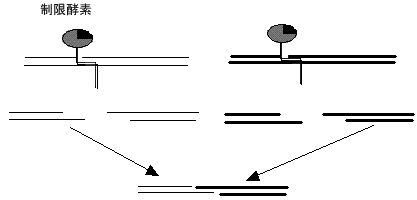 |
||
| ここに、大腸菌の中で増えるプラスミドのDNAとSV40のような動物にがんを作るウイルスDNAがあるとする。それぞれを同じ制限酵素で切断し、混ぜれば、がん遺伝子の乗ったSV40DNA断片と、複製に必要な遺伝子部分を持ったプラスミドDNAが一つになり、がん遺伝子を持った大腸菌でも増えられるプラスミドを得ることが出来る。実際は、DNAが複数の場所で切れたりしてそう簡単にはいかないが、兎も角上手くいけば、がん遺伝子を持ったプラスミドを持つ大腸菌が取れる。このような実験の可能性をPaul Bergらが示したのは、1971年の春である。 「こんな大腸菌が動物や人間にとりつけば、人間はたちまちがんになってしまうかも知れない」、そんな心配が科学者の頭を横切ったとしても不思議ではない。又、この技術を使えば、人間の遺伝子を持ったバイキンが出来る訳である。神の摂理に反すると考える人が出て来る。Paul Bergらは、直ちに、SV40遺伝子を持ったラムダファージを大腸菌で増やす実験を中断した。 この状況を「広島原爆投下の前夜かも知れない」と捉えた科学者達の提言により、1973年1月に第一回のアシロマ会議 (Asilomar I)が開催された。主催者の一人であったPaul Bergは、この会議の終わりに、「慎重な立場をとるならば、用心する事と、どのような危険性があるのか、その可能性を見極める為の真剣な努力が要求される」と締めくくった。 先に紹介したRecombinant DNA Controversyの著者FredricksonがNIH所長に就任したのは1974年であり、そこから米国のNIH組み替えDNA指針の作成が始まる。詳細は上記著書を直接読む事を勧めるが、政治的な要因も絡み、「指針か法律か」と云った、2002年現在日本で論議されているような事が延々と議論されたようである。結果として、1976年6月にNIH Guidelinesとして公表される事となる。 NIHガイドラインの公表に前後して、マサチューセッツ工科大学やハーバード大学のあるケンブリッジで、市議会がP 3、P4実験を3ヶ月差し止め(moratorium)、Cambidge Biohazards Committeeを作った。Fredricksonによれば、この委員会は指針を一部の科学者よりは余程良く勉強し、その後の組み替えDNA実験についてはより積極的な役割を果たした、と云う。又、以上の差し止め措置も長く続かなかった。 以上の事件は、その後、いわゆる市民団体のバイオテクノロジー反対運動に於ける大きなモメンタムとなった。その後の米国での経過が正確に我が国に伝わらないこともあり、当時から30年経った現在でも、「市民グループ」がアシロマ会議とケンブリッジのDNA組み替え実験禁止を議論に使っているのが見受けられる。 その後の状況については、ここでは詳しく述べないが、 NIHガイドラインをベースに各国で組み替えDNA指針が作成された。我が国でも、各省庁が指針を作成し、実験内容によっては審議会審査を行い「大臣確認実験」として安全の確保に努めている。30年近い経過の中で、経験が蓄積され、初期よりも審査手続きなどは簡素化されるようになっている。今までの処、重大な事故は1件も生じていない。 組み替えDNA実験は、その後、生命現象の解明には不可欠の武器となった。遺伝子を細胞に入れればそのままその遺伝子が発現することはない事も、組み替えDNA実験で明らかになった。細菌、動物細胞、植物細胞で遺伝子発現に必要な酵素も違うし、制御領域も違うので、ウイルスのがん遺伝子を大腸菌に導入しても「発がん大腸菌」にはならない。 大腸菌のDNAが動物の細胞に取り込まれ、染色体に組み込まれ、その発現によりがんを作る事も考えられなくはないが可能性は非常に低い。それでも我が国の指針ではP2実験として物理な封じ込めレベルを高くしている。しかし、一方、このように理論的には否定出来ないが、実験的には証明出来ないようなリスクをどう評価するのかは、現在大きな問題となっている。 |
||