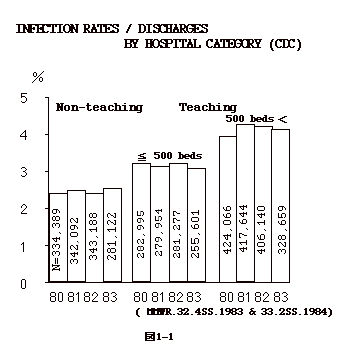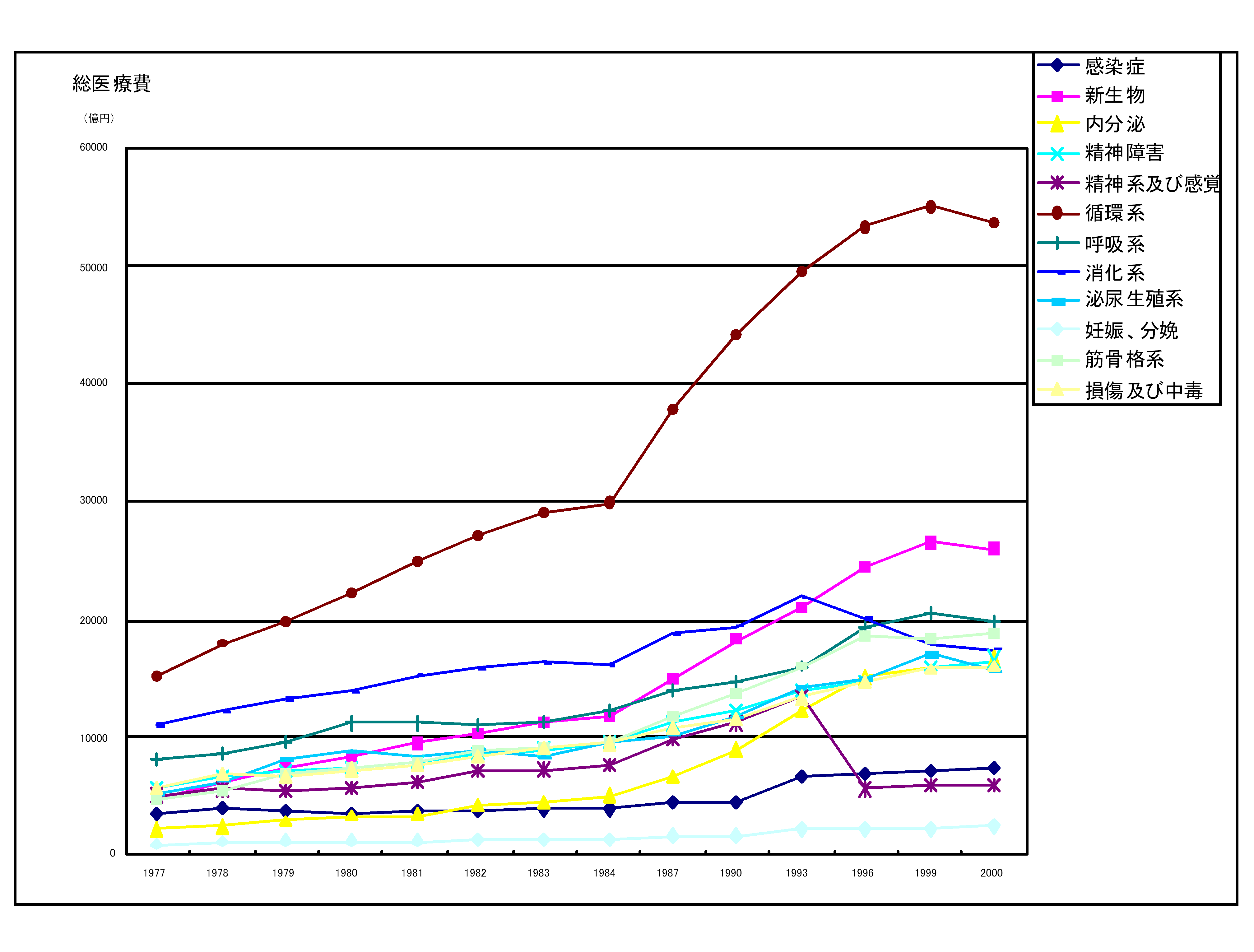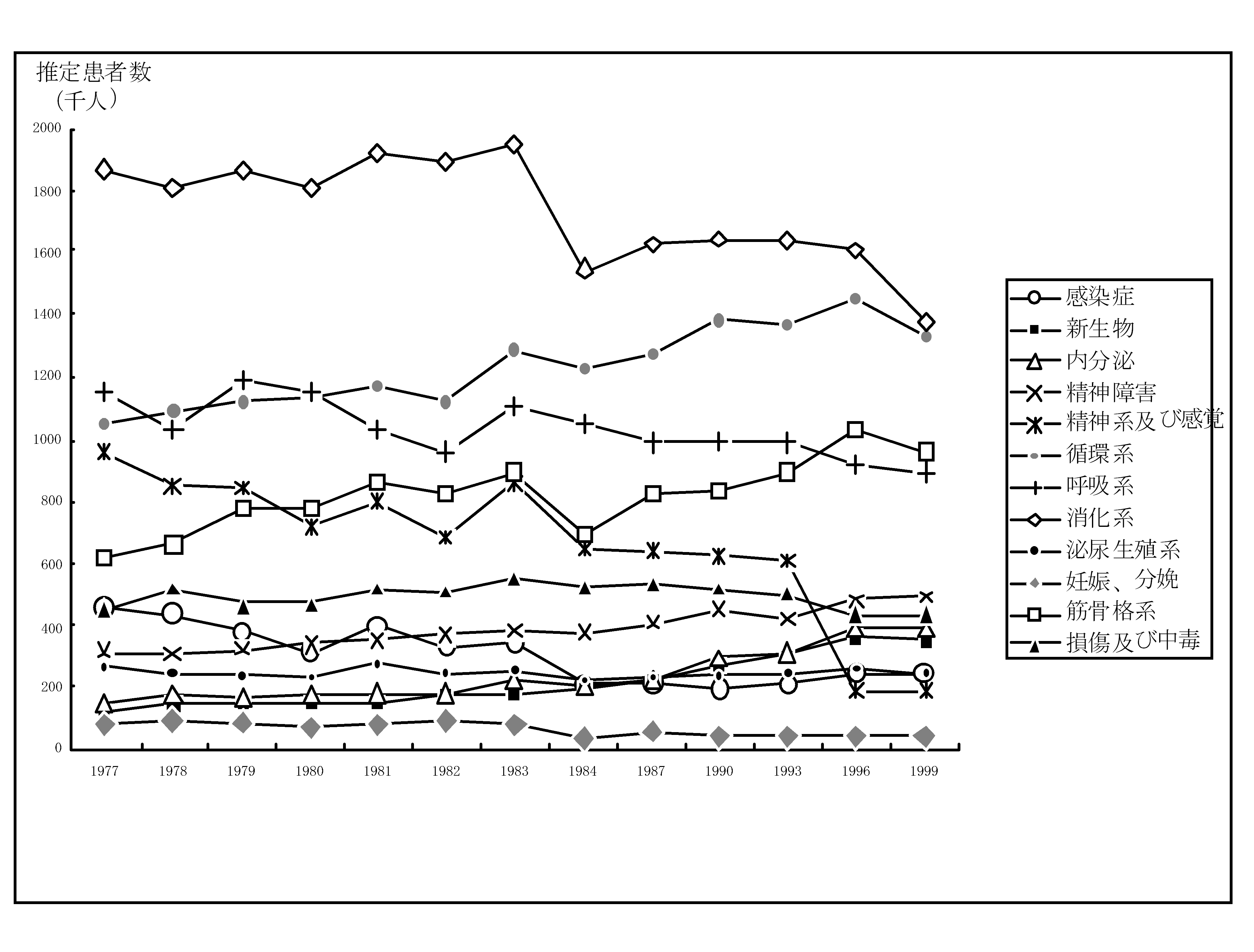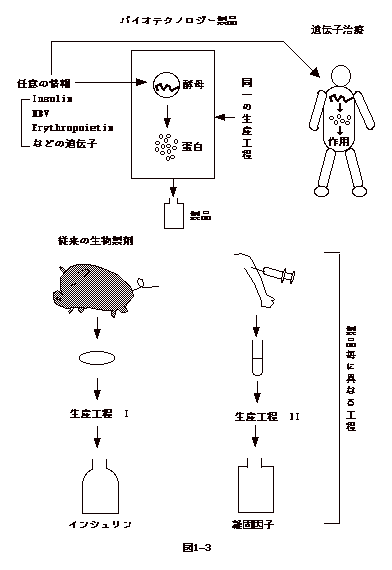第1章 微生物学と社会 |
|
| 微生物はそれだけで一つの世界を作り上げる。動物と違い、遺伝的に同一の生物を無限に研究材料として使える。この為、生物学の多くの基本原理は微生物学から得られた。 しかし、微生物学には社会的要求がある。例えば、
それぞれにつきやや詳しく説明する。 1−1:病院感染500床以上の教育病院と200床以下の非教育病院では、前者の方が遥かに感染率が高い(図1-1)。何故か? (1)侵襲の大きい高度治療を行い、且つ(2)施設規模が大きいので管理が難しい為と考えられている。従って、病院感染は高度な医療を行う病院であればそれだけリスクは高くなる。 |
|
|
|
| 米国の統計によると全病院経費の15%が病院感染
にあてられているという。病院感染はその治療費のみならずベッドをその分占有し、医療の効率を下げる。 患者の苦痛は無論である。がん患者の直接死因の大部分は病院感染であり、全病院死亡の15%が感染によると云う(Inlander Levin Weiner: Medicine on Trial,Pantheon,1988)。 対策は、恒常的な病院感染の監視、スタッフ 及び患者の教育、設備の衛生管理、outbreakに対する適切な対処である。この為には、院内感染対策委員会、感染コントロール担当者(infection control doctor及びnurse)、十分な予算措置が必要である。 しかし、最も重要なのは「院内感染は常に起こり得る」、と云う認識である。わが国では、「病を治す病院で患者に病気をうつすなどあってはならない」とされた。「あってはならない」ので、実際起こると隠さざるを得ない。それが事態を更に悪くさせた。 私が東大に移って間もなくMRSAの院内感染が広がり死者が出た。富家さんが東大病院でMRSで亡くなったご主人の事を新潮+45に書かれた。対策において当初最も困難であったのは、各部局での院内感染の存在を認めない事にあった。 医療事故、薬の取り違え、患者の取り違え、と云う信じられないような事故は、病院組織が大きくなればなる程、起こる可能性は増す。チャートの上では、効率が上がる。しかし、組織が大きければ医療担当者の間の直接の連絡は減る。お互い顔を見たことのない医療スタッフの間を患者は廻されて行く。過去に、200床以下の病院の統廃合が行革絡みで、強力に推し進められた経過がある。本当に、統合が医療として効率が良いのか、再考すべき時期ではないか。 <問い>医療技術が進めば、病院感染のリスクは減少するか?考えを述べよ。 1−2:開発途上国との関係日本の国民医療費は毎年5%前後増加を続け、1995年には27兆を越え、2001年には31.3兆円、国民所得の8%強となっている。これは、国民所得の7%位になる。医療費の上昇は保険制度を破壊する。 医療費の上昇は疾病により大きく異なる。一見感染症の医療費は殆ど増えていない。これは日本の統計では直接の死亡原因としての感染をカウントしないためである
(図1-2)。
|
|
日本の医療費:患者数と医療費の年次変化 |
|
1−3:遺伝子組換え技術と社会遺伝子の組換え技術は食品、医薬品、環境対策と広く利用されている。最近遺伝子治療の導入とゲノムプロジェクトの進展も加わりその社会的影響のあり方が変わりつつある。医療面で考えてみる。 インシュリン、エリスロポイエチン、下垂体ホルモン、血液凝固因子など沢山の生物製剤が医療に使われている。従来はそれぞれの臓器から精製し製造過程も製品独自のものであった。つまり、製品毎に設備、技術開発が必要であった。しかし、組換え技術で酵母、あるいは動物細胞を使用する生産ラインが出来れば、導入するDNAの塩基配列を変えることでB型肝炎ワクチンからすぐインシュリン生産などにスイッチが可能である。つまり、医薬品生産は原料ベースからDNA(=情報)ベースに移行しつつある。 この事は、一度生産設備と技術が定着すれば、塩基配列という情報を得るだけで物を作れるという事である。一方、正しい塩基配列を得、製品の安全性を確かめ臨床試験を行うには莫大な資金と時間、並びに研究開発が必要になる。つまり、開発にはより大きい投資を必要とするがコピーは容易になる筈である。丁度、CDをコピーするように。したがって、今後、技術移転と知的所有権の問題は大きな問題になるであろう(図1-3)。 |
|
|
|
| 遺伝子治療が実用化され広く使用される様になればこの問題は更に重要になる。何故ならば、遺伝子治療は究極的に「人体に遺伝子の配列を導入し、後は人体がそれを発現させ治療的に機能すること」を基本とする手法だからである。つまり、本質はATGCをいかに並べるかという処に来るからである。 遺伝子組換えは汎用性があり、従来の技術より、より急速にしかも広く拡散する性質を本来持っている。 血液製剤によるエイズ禍は大きな社会問題となった。この様な事態を克服するため、今後ヒト、動物由来の製剤は次第に遺伝子組換えによる製剤に変ると考えられる。 1−4:安全性をどう考えるか微生物学の関わる色々な局面で安全性の問題に直面する。危険性が明らかな場合は、考え方として、問題は比較的単純である。ここでは、少しややこしい状況を考えてみる。 ボツリヌス毒素を局所に注射すると局部の筋肉の弛緩性麻痺が起こる。この現象を利用し、斜視の患者の収縮している眼瞼筋肉にボツリヌス毒素を注射する治療が行われている。医者が適当な用量を適切な部位に投与すれば患者の利益は大きい。 しかし、この治療にはボツリヌス毒素を工業生産する事が必要になる。ボツリヌス菌を大量に培養し毒素を作らなければならない。作業員の安全性の確保が必要である。現在の技術であると、微生物学の見地から適切と判断される対策が取れるので工場は操業に踏み切る事が可能である。 処が、工場の付近の住民がこの工場からボツリヌス菌が漏れ出る可能性ありとして、危険な施設は他に移転すべきであると訴訟が起きた。工場は万全の対策を立てたと説明しても住民は相変わらず「菌が工場から漏れる確率はゼロではない」として追求を止めない。「小匙一杯で100万人を殺せる。実に危険だ」と主張する。更に、「ボツリヌス菌は生物兵器にも利用出来る。だから、この工場は生物兵器生産工場である、直ちに操業を停止させよ」と訴訟はエスカレートの一方である。 作業場の安全確保については、法律としてもわが国であれば労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等がある。しかし、住民の心配に関しては、対応は非常に難しい。このような問題については、W. W. Lowranceがその著書Of Acceptable Risk; Sciece and the Determination of Safety (William Kaufmann, Inc. 1976) で興味深い記述をしている。彼の考えは次のようである。 安全性の決定は、二つの異なった作業を通してなされる。一つは、リスク評価であり、他は安全性の判断である。リスク評価とは、発生確率や起こり得る災害の程度を評価する作業であり、科学的に対応出来る。一方、安全性の判断は、そのリスクが社会的に受容可能かどうかを判断する作業で、基準作成や政治的判断を伴う。つまり、順序として、先ず科学的リスク評価があり、次いでそれに基づく安全性判断ある。 上の場合、安全と判断するのは、リスクがゼロである為ではない。工業生産の際の事故が起こる可能性はゼロとは云えない、しかし、設備作業工程から、作業員へのリスクは容認出来る位十分低い、と判断する。一方、リスクはゼロではないが、そのリスクは、治療薬による利益を下回ると判断する。即ち、社会的に許容出来ると判断する為である。 ここで、受容可能(acceptable)と云う言葉を使用しているが、これ即ち、「安全性の決定」は相対的且つ判断的作業である事を示している。ここで、「誰の目から受容可能と判断すればよいのか?」「如何なる意味で受容可能とするのか?」「誰にとって受容可能であれば良いのか?」、と云った問題のある事を考慮しなければならない。 そこで、受容可能と判断するには、どのような事を考慮すればよいかと云う事になる。Lowranceの考えを土台に条件を挙げてみると次のようになる。1.妥当性(reasonableness)。米国のConsumer Product Safety Commissionは"reduce unreasonable risk of injury"と云うような表現を用いている 。2.慣用性(custom of usage)。例えば、米国のFDA(Food and Drug Administration;食品医薬品安全局)はgenerally recognized as safeと云うような表現を用いている。3.専門家が認めているやり方であること(prevailing professional practice)。4.実行出来る最善の条件(best available practice, highest practicable protection, and lowest practicable exposure)。5. それを行う事の必要性とそれによる利益。6.明白な危険性の無い事。7.科学的にも明らかに問題のある状況ではないこと。8.過去に職業による暴露の記録(例えば、煙突掃除夫のタールがん)があればそれを参考にする。9.現在ある危険度との比較。例えば破傷風菌は自然環境で沢山存在する。正常人でも10%位の人が腸管に保有している。破傷風菌を扱う実験室の存在は社会に脅威になるか、と云った事である。最後に、公衆の投票もありえなくはないが、安全性そのものよりも政争に於ける利害が入り込む事は注意しなければならない。 安全性の問題に取り組む時、これは微生物の安全性(バイオハザード、biohazard)だけに関わるものではない事を認識する事がまず必要である。人生や仕事の中でリスクがゼロのものは無い、と云う認識が必要である。今晩職場から帰る。飲み屋に寄る。少し酔って地下鉄に乗る。駅を乗り換え、最寄りの駅で降り歩いて家にたどり着く。これがリスクがゼロの行為であるとは、絶対に云えない。飲酒は糖尿病を悪化させるであろうし、地下鉄に乗ろうとしてプラットフォームから転落するかもしれない、歩いていて自動車にはねられるかもしれない。しかし、我々はそれを許容している。つまり、リスクはゼロではないが、一応安全と判断している。むしろ、リスクがゼロでない事を認識し、色々な社会の取り決めが出来ている。道路交通法が良い例である。上の住民運動の議論で考えなければならないのは、この場合に限りリスクゼロを要求している処である。 最近の国際的動向としては、「ゼロリスクの行為はあり得ない」、と云う考えが受け入れられ、そのような言葉が安全管理に関する文書の中に見かけられるようになった。 ボツリヌスの生物兵器への利用であるが、この点は可成り難しい問題を含んでいる。生物兵器禁止条約が結ばれ、このような工場の査察の仕組みが現在検討されている。大切なのは、規則や条約よりも「生物兵器を使用しないと云う世界の世論」かもしれない(L. A. Cole: The Eleventh Plague (1996) Freeman)。 1−5:Precautionary Principle1982年頃から認識され始めたエイズ、その病原体HIVにより汚染した血液製剤による血友病患者のHIV感染、1990年頃から英国を中心に問題になり、2000年の現在ヨーロッパに拡がっている狂牛病(bovine spongiform encephalopathy)、等に対する行政の遅れた対処に対し、ヨーロッパ、日本など世界のあらゆる処で批判があがっている。批判は、危険性を十分察知しなかった科学者、或いは、危険性を指摘した少数の科学者の考えを直ぐ受け入れなかった科学界、へも向けられている。科学が危険性を証明する迄、行政措置が取られなかった事に対しても批判が向けられている。 科学は、その時代に受け入れられている考え、つまり既成概念、を疑ることから始まる。天動説に対する地動説がそうであり、生物自然発生説に対するパスツールの「生命は生命から」と云う考えもそうである。疑る事なしに発見はない。このことは、裏返すと、新しい説に対しても、科学は同様な態度を取る。つまり、如何なる説と雖も疑われずに受け入れられることはない。即ち、科学的事実となるには事実の積み重ね、反論に対する確固たる反証、が必要である。即ち、時間がかかる。後になって「何でこんな事を認めるのに時間がかかったんだ」と新聞は云う。研究者の中にも「自分はそう信じていた」と言い出す者が出てくる。しかし、科学には近道はない。このようなプロセスを経ることにより、科学は自分自身の誤りを正している訳である。 エイズ、狂牛病いずれも発見の初期に於いて、その拡がりと危険性を正確に予見することは困難であった。エイズの原因のHIVは、その少し前に発見された発病頻度の低い成人T細胞性白血病ウイルス(HTLV-1)に似ており、HTLV-IIIと命名された位である。その発病率が100%近い事が分かったのは、数年後である。狂牛病も、種の障壁を越え、しかも肉を食べる事で感染するとは、多くの科学者は思わなかったであろう。このような事から、科学が危険性を証明出来ない状況に於いて如何なる対処をすべきか、と云う事が近年大きな問題となっている。 このような状況から、"precautionary principle"と云う言葉が国際的な取り決めの中で使われ、医薬食品分野にもこの概念を導入しようとする動きがある。日本語では予防原則と訳されるが、英語に訳し戻すと、"prevention principle"となり、"precautionary principle"とは意味が違ってくる。「予防」は、危険性の実態があるもの、例えばインフルエンザ流行、の予防であるが、"precautionary principle"は、実態が分からないものも含めた危険に対し「慎重である」と云う「慎重原則」である。 Precautionary Principleは、国際条約では、1989年の海洋汚染に関し、「廃棄により環境破壊或いは有害な効果が出ると信じる十分な理由が存在する場合、廃棄とその影響の因果関係を示す適切な或いは十分な科学的証拠が無くとも、汚染廃棄を規制し、海洋自然環境を守る為の効果的なprecautionary approachの必要がある(一部意訳)」(Nordic Council's Conference on the Pollutioin of the Seas)と云う文章で初めて現れている。そして、1990年のThird International Conference on the Protection of the North Sea (ICNS)では、「閣僚は、廃棄と影響の間の因果関係を証明する科学的根拠が無くとも、環境中に残留し、毒性を持ち、生物に蓄積される物質によって起こり得る破壊効果を避ける為、行動を起こすと云うprecautionary principleを今後も適用することを誓約した」となっている。「平たく云えば、科学的な根拠が無くとも、災害の可能性があれば、それを避ける手段を取るべきだ」と云うことになる。海や山の身近な環境破壊を考えても、環境破壊の科学証明がなくても、廃棄を止めるの越したことはない。この原則は当然のように思える。しかし、この原則を他の分野、例えば食品、医薬品などの分野に適用するかについては、論争の中心になっている。特に、国際条約、法規などに組み込むかどうかと云う点では議論が分かれるところである。問題点を幾つか上げる。 先ず、「慎重原則」を適用するには、(1)対象がそれに足る深刻な健康影響を及ぼし得るのか、(2)国或いは個人の間の商取引の自由よりも遥かに重要な問題か、(3)経済的或いは社会構造的に容認出来るか、(4)他のリスクに比較し、採用した手段は度を越えていないか、につき検討する事になっている(Le Principe de Precaution: Rapport au Premier Ministre, Kourilsky & Viney)。ここで、組み替え食用トウモロコシを例に取ると、「組み換えトウモロコシは人がかって食したことがない。安全であるという証拠は無いので、慎重原則を適用し、徹底した仕分けと標識、或いは、販売の禁止、をすべきである」と云う主張がある。これは、上の4項目をクリアしているのか、と云う問題である。 もう一つの問題は、次のようなケースである。ある方法に対し危険性が指摘され、新しい方法が提案されたとする。しかし、新しい方法について、科学的に完全に安全かどうかその時点では分からなかったとする。この場合、どちらが慎重原則に沿った方法なのか、結局は後にならないと分からない。 病気の原因と云う一見行政と関係のないような事についても同様な事が云える。例えば、スモン病の原因はウイルスであると云う説がだされ、その内にキノホルムが原因であることが次第に確実になった。しかし、ウイルス説が出たとき直ちに患者の隔離をするのは、その段階では「慎重原則」に則った処置とも云える。もし、本当にスモンがウイルスである事になったら、直ちにその手段を取らなかったと云う事で行政は訴えられたかも知れない。しかし、そのような「慎重原則」に従った行動を取らなかった事で、キノホルムと言う本当の原因にたどり着いたわけである。つまり、この場合はウイルス説で直ぐ行動しなかた事が「慎重原則」に基づいた行動であったと云う事になる。 この様に考えると、precautionary principleとは何か、と改めて疑問が起こる。結局は、後知恵でこの原則に従ったかどうかが判断されることにもなりかねない。しかし、見方を変えると「科学的証拠が無くとも、判断を行う」と云う「慎重原則」は「判断を科学者に任せず、市民も責任を取る」、と云う原則と解釈する事も出来る。このような考えに立てば、precautionary principleのエッセンスは情報公開、transparency、である。 1−6:新しく出現する感染症と再び出現してくる感染症 エイズ、エボラウイルスなど従来記載されていなかった感染症が社会的な問題になっている。又、ロシアのジフテリアの大流行、南米のコレラ大流行、大都市での結核の増加など一度は消えたと思われた感染が再び猛威を奮い始めている。これは、主に社会構造の変化によるものである。WHOはこの様な状況に対し、感染症の世界的な監視機構の設置を提唱している。又、米国の科学アカデミーの勧告として21世紀には感染症が大きな問題になるとし、その対策の重要性を訴えている。 しかし、考えてみると、情報があってすぐ行動に移せるものではない。国あるいは地方自治体が金を使うにあたっては、それだけの社会的要請が必要である。つまり情報が或程度量的に蓄積されないと、対策には至らない。特に人が経験したことのない感染症については、始めは無視される事もあるし、他方過剰な反応もある。従って危機管理に当たってはこのような社会的要因、経済的要因(cost-benefit)が大きく影響することを留意しなければならない。 もう一つ考えなければならないのは行政の縦割りの問題である。神戸大震災でもこれは大きな問題であった。縦割りは官庁間にもあるし、国と地方自治体、地方自治体間にもある。その原因は役所のナワバリという事で批判されるに止まっているが、大きな要因として財源の問題がある様に思われる。例えばA県の問題をB県が金を出してやる事には大きな困難がある。しかし問題が感染症でAB両県をまたぐ場合にはAB県別々では調査に大きな支障が出る。この様な問題を解決しないと本当の危機管理には至らないのではないかと思われる。 しかし、一番難しいのは、リスク対応の体制を維持する事である。フランスはアフリカと密接な関係があり、実際、パリ市内のパスツール研究所で出血熱ウイルスの分離もした国である。因みに、このウイルスを分離した実験室は隣のアパートと壁を接し(むしろ共有)している。ここで、このようなレベル4も含めての感染症への対策はどうなのか。答えは、定常的監視体制(サベイランス、surveillance)である。わが国で要求されるのは、病院、保健所、地方衛生研究所、国立研究機関、厚生労働省を結ぶ情報網であるが、その維持は容易ではない。 奇異に思うかもしれないが、疾病のサベイランスで非常に苦労するのは、病院の情報の流れと病原体分離の情報の流れを一つのシステムに組み込む事である。日本に限らず、中国、ベトナム、などでも同様で、ポリオの根絶活動の中で身に滲みた事である。 更に大きな困難は、何も起こらない状況での政治的、財政的支持である。 |
|